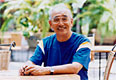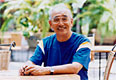|
 奥田のコラム(NO100) 帯津良一先生健康講演会"ときめき養生訓" 奥田のコラム(NO100) 帯津良一先生健康講演会"ときめき養生訓" | ( 2010/11/12 ) |
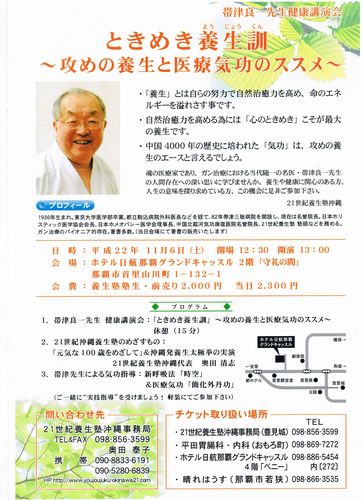








| 
2010年11月6日(土),帯津良一先生をお招きしての沖縄養生塾健康講演会は、今回で15回目という節目の大会になりました。この講演会に足を運んでくださった方々は、予想していた200名をはるかに越える250名近い盛況振りでした。今回の講演会には行政に携わる方々や、ホテルの関係者、お医者さん、それに大学の先生などのお顔も見られ、何かしら21世紀養生塾の"健康づくりの輪"が大きく拡がりそうな気配を感じないではいられませんでした。
帯津先生の講演内容を私なりの理解力でお伝えしようと思います。
①21世紀の健康づくりは、身体(からだ)から、それらも含めて生命(いのち)を見つめる時代になるでしょう。従って医学(療)も、身体と生命の両方を見る時代に変化していくに違いありません。
②『養生(ようじょう)』という言葉の意味も、これまでの、身体をいたわりながら天寿を全うするという"守りの養生"から、生命のエネルギーを養い、溢れさせていく"攻めの養生"へと変えていかねばならないのです。"攻めの養生"としては、中国4000年の歴史に培われてきた「気功」は、そのエースと言えるでしょう。
③「気功とは、正気(せいき)を養う事を目的とした自己鍛錬法」という定義付けがなされておりますが、生命の容れ物である体を養うのが一般のスポーツであるのし対して、体の中身の生命を養うのが気功という事になるのです。
調身(身体を整える)、調息(呼吸を整える)、調心(心を整える)の三つの要素が加わっていれば、どんな動きでも気功の範疇に入ると言って良いのです。大自然、大宇宙、そして虚空と心を一つにして舞う太極拳は、まさに気功の最たるものと言えるでしょう。太極拳は"動く禅"であると言われます。
④21世紀は"攻めの養生"の時代と申しましたが、攻めの養生の最大のポイントは"心のときめき"にあるのです。何でもいいからときめく事が肝心なのです。
江戸時代の名医として知られる貝原益軒は、①好きなものをときめきながら食べなさい、但し食べ過ぎてはいけません。②酒は百薬の長、天からの恵みであるから大いに飲みなさい、但しこれも飲みすぎはいけません。品位を高める飲み方をしなさい、との名訓を残してくれております。
⑤長野県伊那谷に住む「伊那谷の老子」と呼ばれる英文学者の加島祥造さんのときめきは、"何といっても女性が一番"と公言してはばかりません。88歳の現在でも二人の女性に囲まれて人生を謳歌しているそうです。20世紀最大の巨匠と言われるあのピカソも、華やかな異性に彩られた灼熱の人生をおくられたようです。
⑥帯津先生のときめきは"カツ丼"だそうです。帯津先生は豆腐が大好きで、中でも"湯豆腐"は毎日の夕食に欠かせない一品だそうですが、ときめいて食べるのはカツ丼だそうです。
帯津三敬病院の食事指導に携わっておられた料理研究家の幕内秀夫さんの見解では、カツ丼は肉と油ですから本来なら毒なのですが、ときめいて食べれば毒も良薬に変わるのだそうです。ちなみに帯津先生の養生法は「朝の気功と夜の酒」だそうです。
⑦"攻めの養生"のもう一つのエースは"ホメオパシー"なのですが、最近の新聞にホメオパシーにはエビデンス(科学的根拠)がないからやってはいけないとの記事が載り、一部の人達をあわてさせたようです。ホメオパシーが最も盛んなイギリスでは王立のホメオパシー病院があるぐらいで、国が認めた有力な医療法の一つです。先日の新聞報道の裏には、何かしらの大きな力が隠されているとしか思えてなりません。
⑧ホメオパシーとは、ドイツの医師サミエル・ハーネマン(1755~1843)によって体系化されたエネルギー医学です。ホメオパシーとは、自然界の物質を徹底的に希釈して物質性を排除し、そのエネルギーだけを人間の生命に注ぎ込む事により、生命力の向上をはかるのです。
ホメオパシー医学は、患者さんの話を徹底的に聞いて、その全体像をつかむ事から始まるので、今、世界で行われている医学の中では、最もホリスティックな医学と言えるのです。
⑨西洋医学は、目に見えるものしか信じない世界です。しかし、人間の生命体は目に見えないものの方がはるかに多いのです。ホメオパシーはその目に見えない世界に目を向ける医療です。
生きている事の中には、勘を働かせたり、喜んだり悲しんだり、泣いたり笑ったりという感情に生きている部分が殆どで、エビデンスだけではどうにも説明が出来ないのです。
⑩人間は明るく前向きだけでは生きてはいけません。人間の性(さが)は、本来、寂しさや悲しみが根底にあるのです。はるかな虚空から一人でこの世に生を受け、いずれはまた一人で虚空に旅立っていかねばならない不安の中に人は生きているのです。その不安や寂しさや哀しさを土台に据えて、希望の種をまき、育て、花を咲かせていく人生こそが一番強い、本物の人生となっていくのです。
⑪人生の最終の目標は、"青雲の志"を抱いて生きる事にあるのです。青雲の志とは聖賢の人になろうとする志です。聖賢の人とは、生涯を通して、いささかなりとも世のため人のためにお役に立てる志に溢れた人の事です。青雲の志には終わりは無いのです。
⑫いい人生を送っている人はいい顔になってきます。立身出世やお金儲けの上手な人がいい顔になるとは言えません。帯津三敬病院には「気功道場」があって、やがて30年になるのですが、その道場にやってくる人達は、体は病気であっても、気功を通して実に素晴らしい顔になっていくのです。
気功にはそれだけの力があるのでしょう。
⑬「気功的人生」を生きられる事をお勧めします。気功的人生とは、物事にとらわれない事、そして、私達は遥かなる大宇宙、虚空と繋がって生きている事を意識の中心に置く事、そして、その中に生かされて生きている事への感謝の心が深ければ深い程、人生は感動に満ちた人生になっていくのです。皆さんどうか素晴らしい感動の人生をお過ごし下さい。(以上帯津先生の講演の主旨です)
*帯津先生の講演の後、帯津先生のご指導で「簡化外丹法」という気功を全員で練功しました。熱気に満ちた素晴らしい会場となりました。本当に有難うございました。 (2010・11・12の記)
写真上:第15回講演会チラシ
写真中:帯津先生講演風景
写真下:帯津先生と「簡化外丹功」の実演風景 | |  |